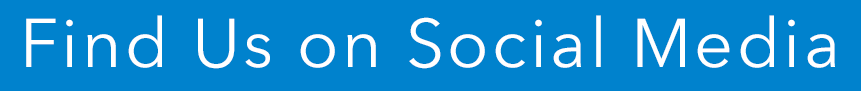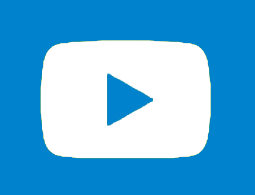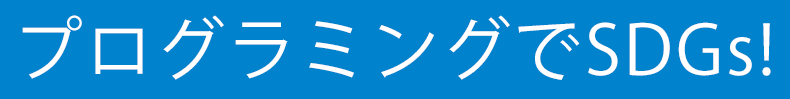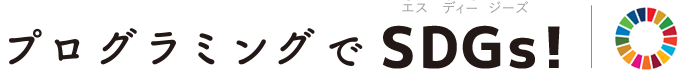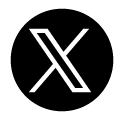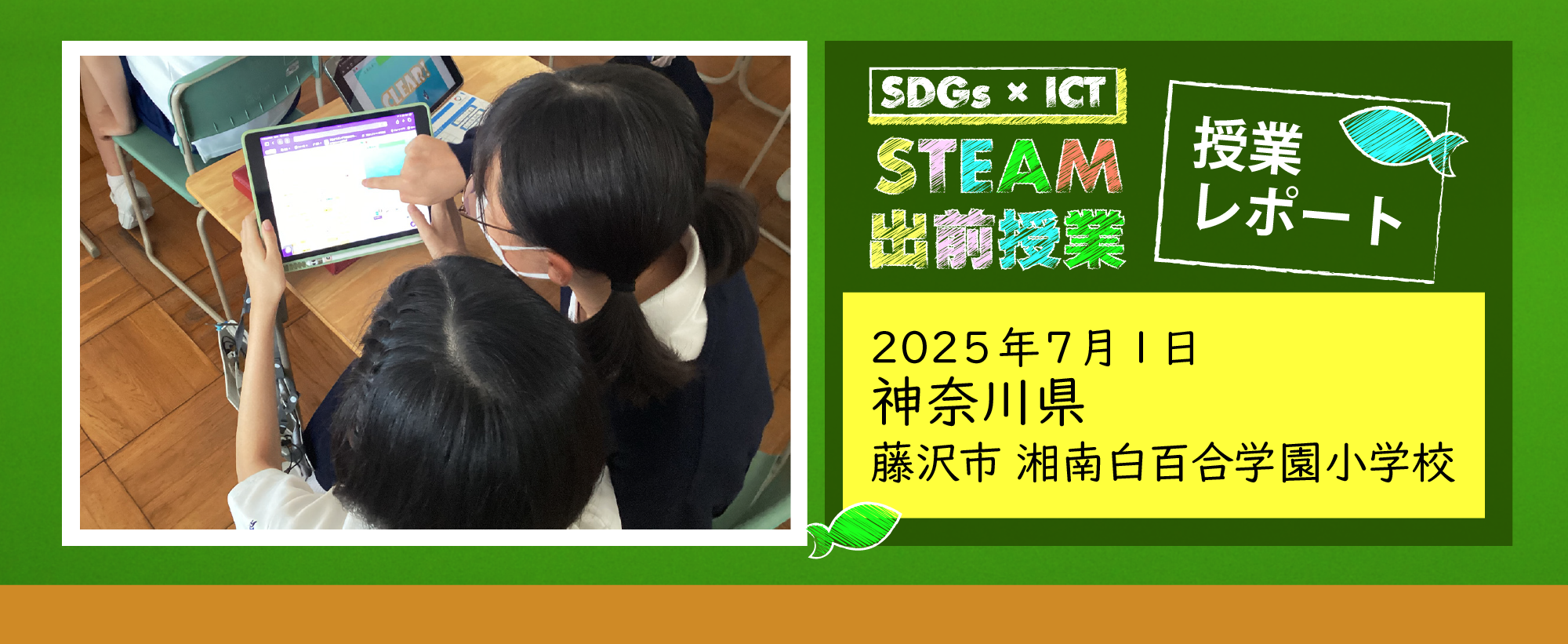開催概要
- 授業内容
- Scratchで海の生き物を救おう
- 日程
-
2025年7月1日(火)1回目 8:45~9:30
2回目 9:40~10:25
3回目 10:35~11:20
4回目 11:30~12:15 - 実施校
- 神奈川県 藤沢市 湘南白百合学園小学校
- 対象学年
- 6年生 (96名)
レポート

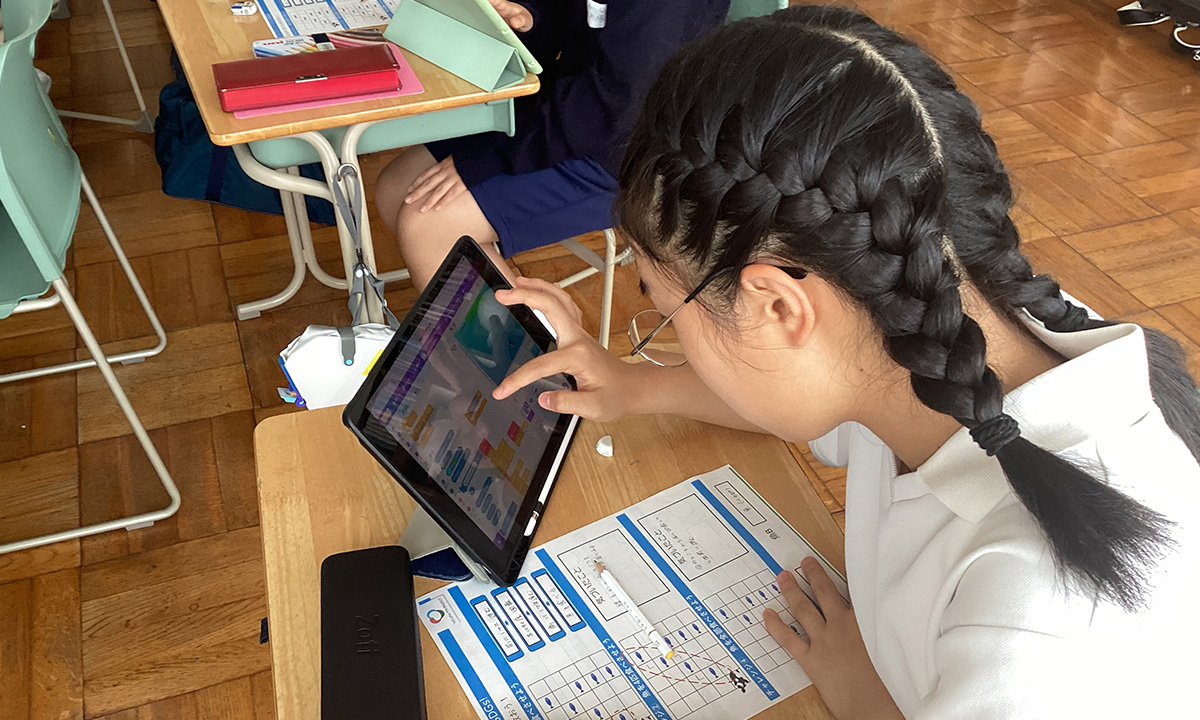
湘南白百合学園小学校6年生の皆さんには、オンライン授業で「Scratchで海の生き物を救おう」に取り組んでいただきました。1~3コマ目では各クラスごとにプログラミングを行い、4コマ目では学年全体で「プラスチックごみ問題」について学びました。
この授業では、お腹を空かせたシャチのキャラクターをマス目上で動かし、順番に魚を食べさせていくというプログラミングを行います。1マス進むごとにエネルギーが減り、魚を食べるとエネルギーが回復する仕組みのため、効率よく魚を食べさせるには、シャチに近い場所にいる魚から順に食べる必要があります。
まず、シャチをマスの上で動かすためのメッセージをワークシートに記入し、動きを確認します。これにより、その後のブロックを用いたプログラミングも理解して考えながら進めることができます。同じ動きを繰り返す際には「くりかえしブロック」を使い、子どもたちは自力で全ての魚を食べさせることに成功しました。ですがゲームクリアになりません。よく確認するとエネルギーが減ってしまう魚を2匹見つけました。シャチが魚だと思って食べていたその2匹はプラスチックだったという設定です。
「魚A」を本物、「魚B」を偽物として、「魚A」だけを食べるようにプログラミングをし、ようやくシャチのお腹をいっぱいにすることができました。
プラスチックは、軽くて丈夫で加工がしやすく、身の回りの色々な製品に利用されています。ですが、自然に分解されにくく、小さくなっても長く環境中に残り続けます。これらの小さくなったプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれています。
「海の生き物がプラスチックを食べるまで」人間がどれだけプラスチック製品を作ったり捨てたりしているかをクイズ形式で紹介しました。みなさんはその深刻さに真剣に耳を傾けている様子でした。
最後の質疑応答の時間では、児童のみなさんから「ごみが増え続けると人間はどうなるのか」や「マイクロプラスチックを食べた魚を食べた魚の内臓も傷つくのか」など、大変興味深い質問を聞くことができました。
SDGsの目標達成は難しいと考える人も多いですが、プログラミングはこれからの課題解決に近づくために「できることが増える」ため、興味を持ったらぜひチャレンジしてみてほしいと伝え講義を終えました。
生徒・先生方の声
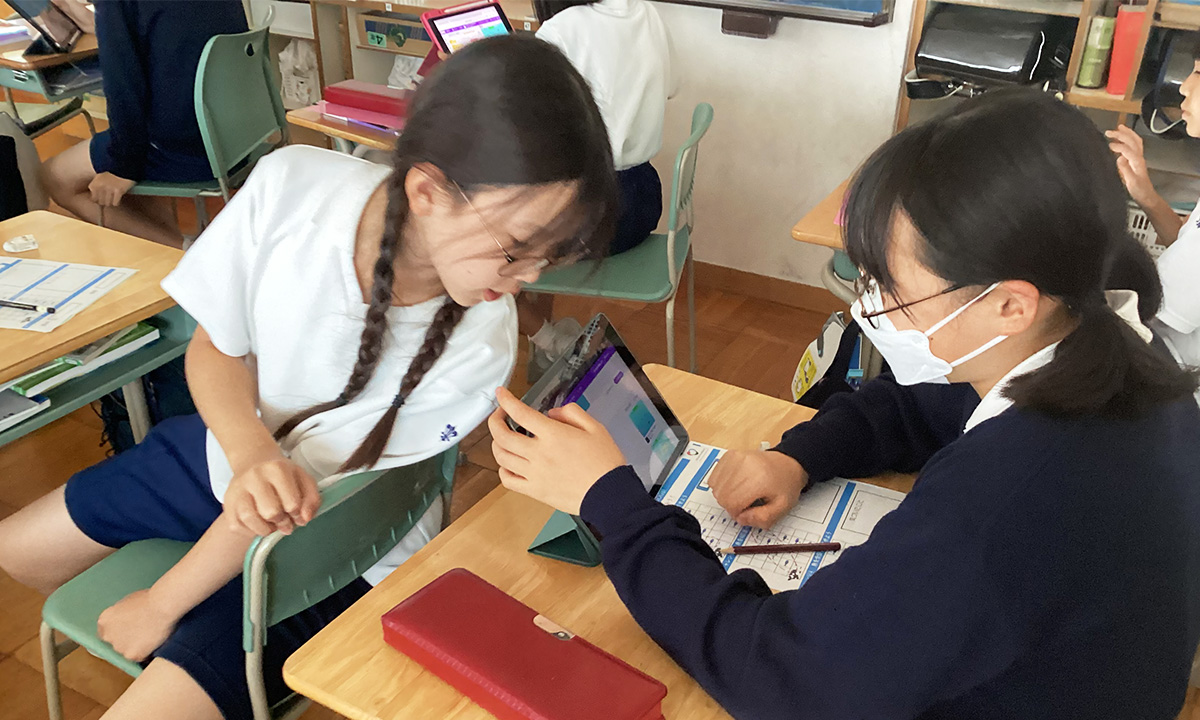

- 海にいる魚のことを良く学ぶ事ができて楽しかった。(小6)
- 海の環境についていろんなところでいろんな人がいろんなことをやっているんだなと思いました。
(小6)
- 私はプログラミングが苦手でしたが、興味を持つことができました。(小6)
- クイズやプログラミングが楽しかったです!(小6)
- たくさんiPadを使えて、長時間学べ、すこし難しくてやりがいがあったので、おもしろかったです。ありがとうございました。これからも、がんばってください。(小6)
共催:一般社団法人 イエロー ピン プロジェクト
後援:文部科学省
協力:リトルスタジオインク株式会社