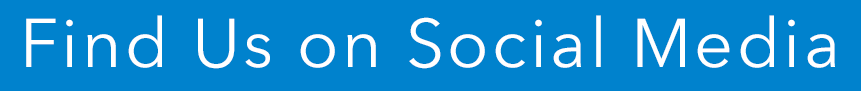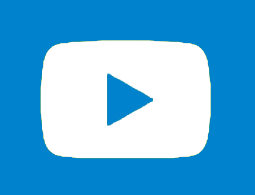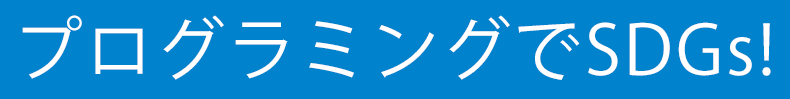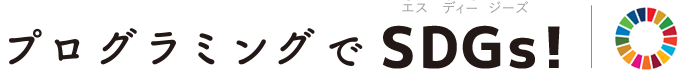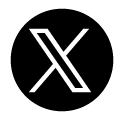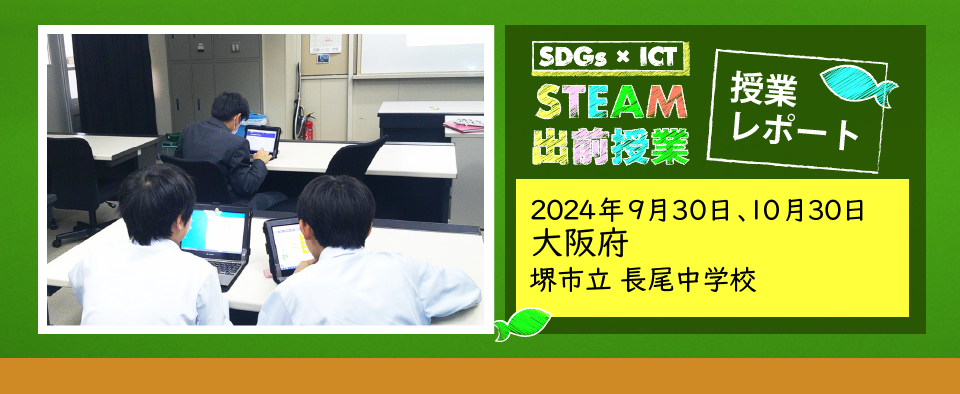開催概要
- 授業内容
- Scratchで森里川海クリーンアップ!
- 日程
-
1回目 2024年9月30日(月) 2回目 2024年10月30日(火)15:50~17:25 15:50~17:25
- 実施校
- 堺市立長尾中学校 情報科学部
- 対象学年
- 1〜3年生 (8名〜30名)
レポート


堺市長尾中学校の情報科学部の皆さんには、今年7月にオンラインで授業で「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。今回のオンライン授業では、その内容をさらに応用した「Scratchで森里川海クリーンアップ!」に挑戦していただきます。
1回目の授業では、まず前回の復習をしました。
「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」はScratch上の仮想の海で、画面上部から落ちてくるCO2を、下にいるアマモが吸収しスコアを獲得できます。CO2を3回吸収するとアマモは消えてしまうので、水中ロボットを動かしアマモを植えていく、というゲームを作成しました。
今回取り組んでいただく「Scratchで森里川海クリーンアップ!」は、基本的なゲームの構造は同じですが、テーマは「森里川海」です。
このゲームは、3つのステージで構成されています。上流では「植林ゲーム」、中流では「プラごみ回収ゲーム」、下流では「下水処理ゲーム」をプレイします。
例えば中流のステージでは、川の画面に上から落ちてくるごみを網でキャッチし、スコアを獲得するというルールになっています。
前回のプログラミングで覚えたことに加えて、背景・落ちてくるもの・ロボット・音などのスプライトを、オリジナルで作っていきます。
2回目の授業では、1ヶ月が経過し、その間に3年生が引退していたため、8名での授業となりました。
ゲームのアレンジをしていく中で、もともとプログラムされている要素を変更する際に制御が難しくなり、ゲームがうまく機能しなくなることがあります。そこで、まずは質問コーナーを設け、生徒たちの疑問に一つ一つ対応しました。「このメッセージやブロックをこう変えたらどうだろう?」と具体的にアドバイスしました。試してみたものを画面の前まで持ってきて現状を見せてくれる生徒も多く、思い通りに動かなくても、自分のプログラムによって何らかの動きが生まれること自体が楽しいようでした。何度も試行錯誤することで、少しずつ理解が進んでいきました。
授業の最後には、自分たちの作りたいゲームを自由に作成し、発表しました。限られた時間の中でも生徒たちの理解は早く、オリジナリティあふれる作品が生まれました。
生徒・先生方の声


- 先生の説明がとても分かりやすくて、改善点にすぐ気づくことができ、たのしかった。(中1)
- 自分じゃ分からなくて困っていたところが解決できたところ。(中1)
主催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト
後援:総務省、文部科学省、環境省
協力:リトルスタジオインク株式会社