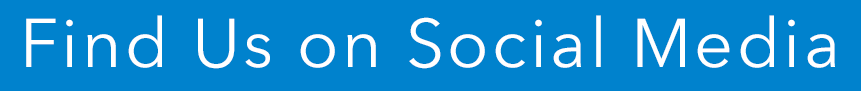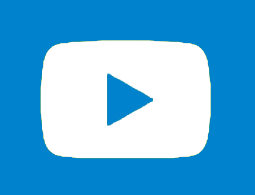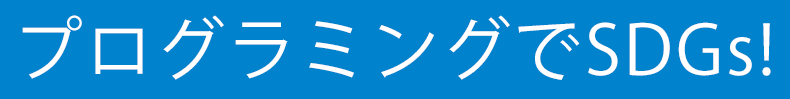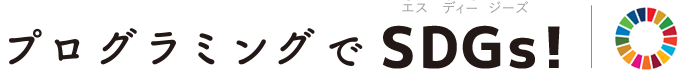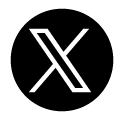開催概要
- 授業内容
- Scratchでブルーカーボンチャレンジ!
- 日程
-
2025年3月11日(火)1回目 8:35~9:20
2回目 9:25~10:10
3回目 10:50~11:35
4回目 11:40~12:25 - 実施校
- 品川区立 芳水小学校
- 対象学年
- 4年生 125名
レポート


品川区立芳水小学校4年生の児童の皆さんには、「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。
事前学習として海洋汚染やわかめの養殖について学び、それを踏まえた上でブロックプログラミングのScratchに取り組みました。
人間の社会活動により大気中に増加している二酸化炭素は、海にも溶け込んでいます。溶け込んだ二酸化炭素は再び大気中に放出され、その量が増えすぎると、海水がアルカリ性から酸性へと傾く「海洋酸性化」がおこってしまいます。そこで、海に溶け込んだ二酸化炭素を固定化することが大切になります。
この固定化の役割りを果たすのが「ブルーカーボン」です。海洋に生息する海藻やアマモなどの海草は、光合成で二酸化炭素を吸収・貯留(固定)する役割を担っています。
「二酸化炭素がたくさんになると何がおこる?」と講師が問うと、挙手をした児童が「地球上の熱が逃げなくなって、地球温暖化になる」と答えていました。アマモの話への反応も良く、楽しく授業が進行していきました。
まずScratchのゲーム画面上にアマモを6つ植えるように、「アマモを植える」というブロックを使用します。Scratch画面の左側にあるブロックパレットという場所には、様々な種類の命令用のブロックが配置されています。児童たちがそれらのブロックを、中央のスクリプトエリアにスライドさせ、ブロック同士を繋げることで、プログラムが組まれていきます。「スタートボタンを表示する」ブロックを使うと、ゲームを開始することができました。
ゲームが始まると画面の上方向から、二酸化炭素のキャラクターがたくさん落ちてきます。プログラミングで植えたアマモが二酸化炭素を吸収してくれるのですが、3回吸収すると消えてしまいます。このままではゲームとして遊べないので、次は、「ボタンアイコンをタッチするとアマモを植えられるロボット」をプログラミングします。ロボットのキャラクターを操作して、アマモがいない場所にどんどん植えていき、二酸化炭素をたくさん吸収すれば得点、吸収できないとマイナス得点となります。ゲームに慣れたら、高得点を出せるよう自分たちでゲームバランスを調整していきます。自分で設定した数値がゲームに反映されるのが面白く、色々と試す中で、1分間に無数の二酸化炭素をゲーム内に発生させている児童もたくさんいました。
二酸化炭素は、多すぎても少なすぎても高得点が取れず、ゲームとしても楽しくありません。現実の二酸化炭素も同じで、アマモなどの海洋生物が海のバランスを保っています。
講義の最後にはアマモを守ることやSDGsの問題解決など、プログラミングが色々なことに役立てていけることを伝え、授業を終えました。
生徒・先生方の声


- 先生のおしえかたが上手。(小4)
- 最後にいろいろなところを変えて、ハイスコアをだすのが楽しかった。(小4)
- プログラミングを作るのが楽しかったです。SDGsについて知るのも楽しかったです。(小4)
- 自分でいろいろへんしゅうできてたのしかった。作ったあとのたっせいかんがよかった。(小4)
- とてもやさしくおしえてくれて、うれしかった。しくみもかんたんですごいと思った。(小4)
- 難易度として、話を聞いて分かるものだったため、子供たちも飽きずに取り組めたと思う。(教員)
- 子どもたちが興味を持って(ゲームを通して)SDGsのことを知ることができた。(教員)
共催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト
後援:総務省、文部科学省、環境省
協力:リトルスタジオインク株式会社